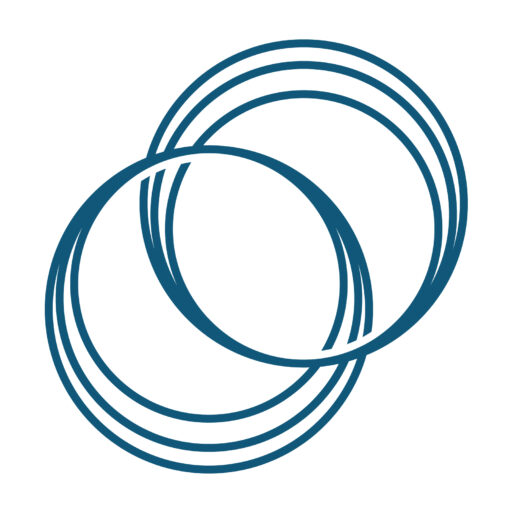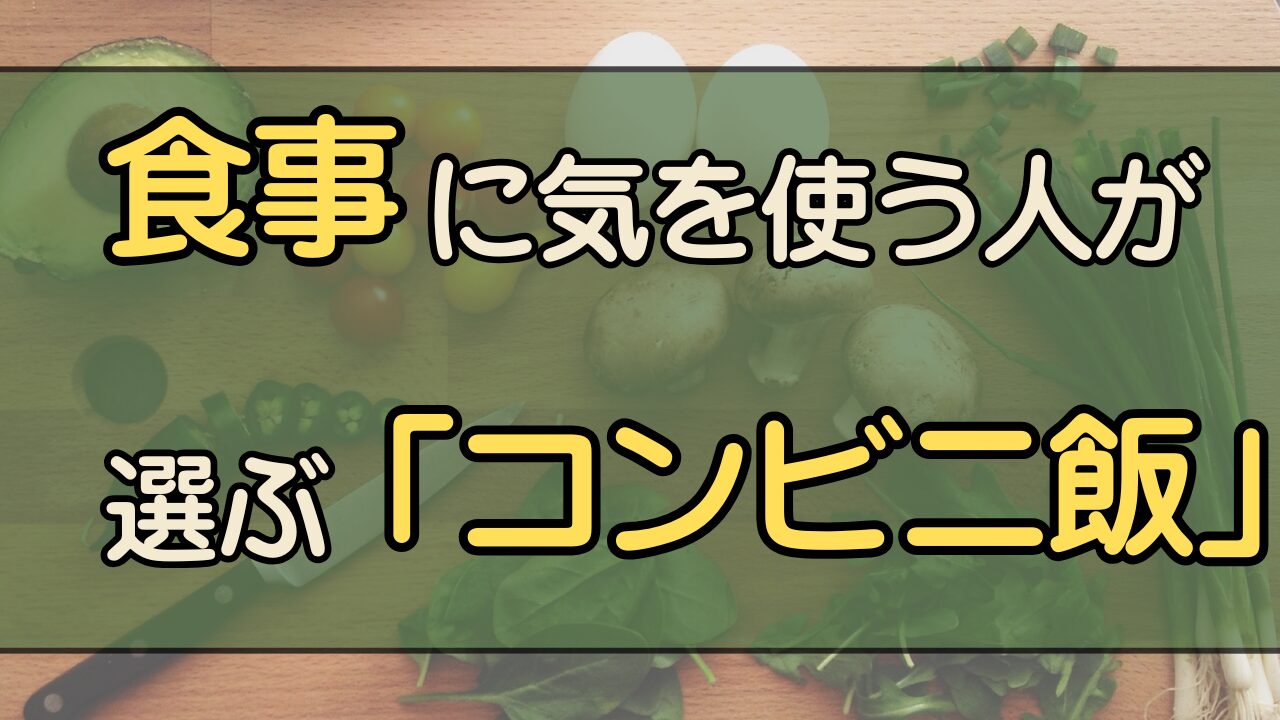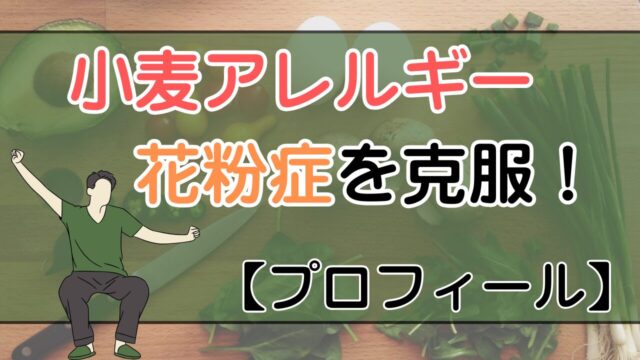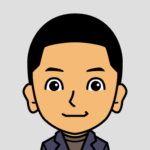①「コンビニで買うのは健康に良くないけど、コンビニしか、選択肢がない」
②「病気になりたくはないけど、コンビニで何を選べばいいか迷う」
①・②のどちらか該当した方はぜひ読んでいただきたいです。
食事療法だけで花粉症、小麦アレルギーを克服した私が、
どうしてもコンビニに行ってしまう時に、
気をつけているコンビニでの買い物の仕方を解説
結論は「おにぎり」

お菓子欲しいな・・・
そう思っても、「おにぎり!」
推奨はこの4つ
「塩むすび」
「梅」
「鮭」
「昆布」
変なものを買うくらいなら、シンプルなおにぎりが一番いいです。
なぜなら、他にいいものがないから。
でも、これだと、
「何に気をつけていいのか」
「何がいけないのか」
がわからないと思います。
避けるべきもの、いいと思ってるけどダメなものを
理由も含めて解説させていただきます。
避けるべきもの
・洋風おにぎり
・小麦系全般(パン、サンドイッチ)
・甘いもの
理由を解説します!
甘いもの

甘いものですが、種類は様々ありますが、
特にデザート、アイス、菓子パン、清涼飲料水など・・・
虫歯になったり、精神疾患に繋がったり、糖尿病になったり、様々な症状につながります。
「甘いものは中毒性があります。」
辞めるまでは根性が必要ですが、
「自分は中毒なんだ。」
という自覚を持って絶って欲しいです。
詳しい説明はここでは割愛します。
洋風おにぎり

「身土不二」
という言葉があります。
その地にあるものには理由があります。
昔のおにぎりに洋風などあったと思いますか?
日本に昔からあるもの(漢字で表記されているもの)
を選ぶようにしましょう。
「梅」「昆布」「塩」「和布(わかめ)」「鮭」などなど、、、
避けて欲しい、一番の理由は、
おいしくするために、
「甘いもの」「植物油脂」
をはじめとした、多くの添加物を含みます。
甘いものは記載した通りです。
油も同じように中毒性があります。
何となく、言われてみると実感することがあると思います。
ポテトチップスなどがわかりやすいですが、
なぜか、食べ始めると止まらないものです。
油を起因とした病気も多いです。
油に関しては話すと長いので、また別の記事にしたいと思います。
小麦系全般
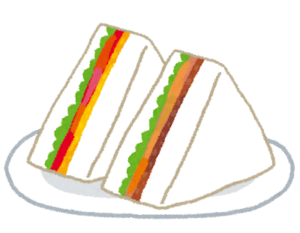
バンやサンドイッチなど、手軽に食べれるものが多いです。
小麦は特にアレルギーや、がんの原因になることがわかっています。
腸内が小麦に含まれているグルテンによって、リーキーガット症候群などを発症し、
免疫異常により様々な自己免疫疾患が懸念されます。
小麦は色々なところに潜んでいますので、
気をつけていても食べてしまうこともあるかもしれません。
パン、サンドイッチ、お菓子全般、揚げ物、うどん、パスタ、そば などなど。。。
「そば」は正当化されやすいですが、
コンビニやスーパーなどのそばの原材料を見てみると、
原材料名:小麦粉、そば粉・・・・
の順番で記載されていることが多いです!
「それでよく、そばを名乗れるな!」
と思ってしまいます。
いいと思って買ってるけどダメなもの

・干し芋
・バナナ
甘いものの正当化。
甘いものを正当化して、甘いものを食べる理由を作ってる可能性が高いです。
知らず知らずのうちに食べているものがあったりします。
同じ糖分なので気をつけましょう。
ちなみに、バナナの糖分は凄まじいです。
下記を参考にしてください。
-
ブルーベリー(生)100gあたりの糖質:9.6g
-
バナナ(生)100gあたりの糖質:21.4g
バナナ1本(約100g)の糖質 ≒ ブルーベリー約107粒(214g)の糖質
まとめ
「ダメなものばっかりで、何を食べたらいいの!!」
ってなりますよね。
でも実際すごく中毒性があるものが多く、食べ続けてきた結果、
日本人の病気の割合はどんどん増加しています。
このような不健康で、病気と常に戦わなければいけない身体になるのは避けたいです。
しかし、実際のところ、
食事はストレスなく、いろいろなものを食べれる方がいいですよね。
個人によって病気に対しての食事の指導は異なります。
自分の体にとってはどんな食事がいいのか。
どのように付き合っていけばいいのか。
相談したい方は、ぜひプロフィール欄の
LINEかInstagramからご相談ください。🙏